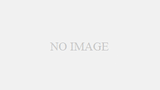インバウンド観光客が「ちょっと苦手…」と感じがちな日本食の正体とは?
インバウンド観光客にとって魅力的な日本食。寿司、ラーメン、天ぷらなどは世界的に人気ですが、すべての日本食が彼らに同じように受け入れられているわけではありません。中には、文化、習慣、宗教、あるいは単に慣れない食感や見た目のインパクトから、「ちょっと苦手だな」と感じられてしまう料理も存在します。
インターネット上の口コミや旅行者の声、各種調査から見えてくる、インバウンド観光客が日本の飲食店で避けがちな料理には、ある程度の傾向があります。ここでは、それらの傾向を踏まえつつ、具体的にどのような料理が挙げられやすいのかを見ていきましょう。完全に網羅した「TOP20」として断定することは難しいですが、多くの外国人観光客が戸惑いやすい料理として頻繁に名前が挙がるものを中心にご紹介します。
例えば、以下のようなものが挙げられることが多いです。
- 生卵を使った料理: 卵かけご飯やすき焼きのつけだれなど
- 納豆: その独特の粘り気と風味
- 内臓系の料理: ホルモン、白子、あん肝など
- 特定の魚介類: ウニ(生)、イカ、タコ(生または歯ごたえのある調理法)、なまこ
- 餅: その粘り気と喉に詰まりやすい特性
- 梅干し: その強烈な酸味としょっぱさ
- 一部の漬物: ぬか漬けなど、独特の発酵臭や風味
- 特定の海藻: もずくなど、強いぬめりのあるもの
- 山菜: 独特の苦みやえぐみがあるもの
- わさびやからし: その強い辛味
- こんにゃく: 独特の食感
- おでんの特定の具材: ちくわぶ、はんぺんなど、地域や具材による違い
- 汁物やおひたしの出汁に使われるかつお節や昆布の風味: 慣れない風味として感じられることも
- 見た目のインパクトが強い料理: イカの塩辛、くさやなど
これらの料理がなぜ苦手とされがちなのか、その背景には様々な理由があります。単に「美味しくない」というよりは、異文化理解や食習慣の違いに起因することがほとんどです。
なぜ「苦手」と感じるのか? インバウンド観光客の食文化と背景
インバウンド観光客が特定の日本食を苦手と感じる背景には、彼らが育ってきた文化や食習慣が深く関わっています。それぞれの理由を具体的に見ていきましょう。
生食文化の違い
日本の生食文化は世界でも類を見ないほど豊かですが、全ての国で生食が一般的ではありません。特に、生卵はサルモネラ菌のリスク管理が徹底されている日本だからこそ安心して食べられるものですが、多くの国では卵を生で食べる習慣がなく、衛生面への懸念から抵抗を感じる人が多いです。すき焼きのつけだれとして提供される生卵に戸惑う外国人観光客は少なくありません。
刺身についても、新鮮な魚介類を生で食べる文化がない地域からの観光客にとっては、見た目や食感に抵抗がある場合があります。特に、ウニや特定の貝類など、風味や食感が独特なものは好き嫌いが分かれやすい傾向にあります。
発酵食品への慣れの違い
日本の食文化を語る上で欠かせない発酵食品。納豆や味噌、醤油、漬物など多岐にわたりますが、その中でも納豆は特に外国人観光客が苦手と感じる代表格です。あの独特の粘り気と発酵臭は、慣れていない人にとっては受け入れがたいもののようです。「腐っているのでは?」と誤解されることさえあります。また、ぬか漬けのような伝統的な漬物も、その独特の風味や酸味に戸惑うことがあります。
内臓食文化の違い
日本では、牛や豚の内臓を加工したホルモン焼きや、魚の白子、あん肝などを珍味として珍重しますが、これも多くの国では一般的な食材ではありません。内臓を食べる習慣がない外国人観光客にとっては、見た目への抵抗感が強く、食べるのをためらってしまうことが多いです。
食感の違い
日本の料理には、海外ではあまり見られない独特の食感を持つ食材が多くあります。例えば、餅の強い粘り気は、食べる際に注意が必要であると同時に、その食感自体が苦手な人もいます。なまこのプリプリとした、あるいはコリコリとした食感や、オクラや山芋のネバネバとした食感も、慣れていない外国人にとっては驚きや戸惑いを与えることがあります。こんにゃくの弾力のある食感も、独特だと感じられるようです。
見た目のインパクト
料理の見た目は、食欲をそそる重要な要素ですが、時には文化的な違いから敬遠される原因にもなります。例えば、イカの塩辛のような見た目が生々しく感じられたり、地域によっては「くさや」のように強烈な匂いを放つ発酵食品は、口にする前にその見た目や匂いで抵抗を感じてしまうことがあります。なまこや白子なども、その独特の形状から食べるのをためらわれることがあります。
宗教的な制約と食の禁忌
イスラム教徒の方にとっては豚肉やアルコールが禁じられているハラール、ユダヤ教徒の方にとってはコーシャといった宗教的な食の規律があります。また、ヒンドゥー教徒の中には牛肉を食べない方がいます。こういった宗教的な背景を持つインバウンド観光客にとっては、食材に含まれる成分や調理方法が非常に重要になります。たとえ好まれない料理リストに入っていなくても、これらの制約に配慮されていないメニューは提供できません。
ベジタリアン・ヴィーガンへの対応不足
近年、健康志向や倫理的な理由から、ベジタリアン(菜食主義者)やヴィーガン(完全菜食主義者)の方々が増えています。日本の多くの料理には、意図せずとも動物性の出汁や食材が使われていることが多く、見た目は野菜だけでも実は食べられない、というケースが発生しがちです。彼らに対応できるメニューが少ないことも、日本の飲食店で食の選択肢が限られると感じる要因となります。
アレルギーへの懸念
食物アレルギーは世界共通の課題ですが、日本のメニュー表示や情報提供が不十分な場合、外国人観光客は不安を感じます。特に、蕎麦や小麦、卵、乳製品、ピーナッツなど、アレルギーを引き起こしやすい食材の使用状況が明確でないと、安心して食事をすることができません。
このように、インバウンド観光客が特定の日本食を苦手と感じる理由は多岐にわたります。これらの背景を理解することは、彼らにおもてなしをする上で非常に重要です。
「苦手」を克服し、「大好き」に変えるための実践的アプローチ
インバウンド観光客に避けられがちな料理があるからといって、それらの提供をやめる必要はありません。重要なのは、なぜ苦手と感じるのかを理解し、彼らが安心して、そして楽しく食事をするための工夫を凝らすことです。ここでは、具体的な対策と、国内外の成功事例を見ていきましょう。
1.多言語対応メニューと詳細な情報提供の徹底
これはインバウンド対応の基本中の基本ですが、その質が非常に重要です。単に料理名を翻訳するだけでなく、どのような食材を使っているのか、どのような調理法なのか、アレルギー情報はどうかなどを具体的に記載することが求められます。
- 写真付きメニュー: 料理の見た目を事前に伝えることで、安心して選んでもらえます。特に、内臓系や見た目のユニークな料理は写真が必須です。
- 食材の解説: 料理に使われている食材が何か、簡単な説明を加えます。例えば、「納豆は発酵させた大豆で、日本の伝統的な健康食品です」といった一文があるだけでも、抵抗感が和らぐことがあります。
- アレルギー情報の明記: 主要なアレルゲン(小麦、卵、乳、落花生、そば、えび、かになど)について、料理に含まれているかどうかを明確に表示します。アイコンなどを活用すると分かりやすいでしょう。
- 宗教的配慮(ハラール、ベジタリアン、ヴィーガン)の明記: 対応可能なメニューには、その旨を明確に表示します。「ハラール対応」「ヴィーガン対応」といった表示があるだけで、対象となるお客様は安心して選べます。対応できない場合でも、その旨を伝えることが誠実な対応です。
多くの飲食店がQRコードメニューを導入しており、これにより多言語対応や情報更新が容易になっています。京都のある老舗料亭では、英語のメニューに加えて、各料理に使われている旬の食材や、料理に込められたストーリーを短いエピソードとして添えることで、単なる食事を超えた文化体験として提供し、外国人観光客から大変好評を得ています。
2.調理方法の調整や代替メニューの提案
苦手とされる食材でも、調理法を変えたり、代替となるメニューを用意することで、提供の幅が広がります。
- 生卵の加熱オプション: すき焼きの場合、生卵ではなく加熱した卵や、割り下を調整するなど、生卵を避けたいお客様向けの選択肢を用意します。卵かけご飯も、温泉卵に変更するなどの対応が考えられます。
- 納豆のアレンジ: 納豆チャーハンや納豆オムレツなど、他の食材と組み合わせたり、加熱したりすることで、納豆独特の風味や粘り気を和らげ、比較的食べやすくアレンジしたメニューを提供する。
- 苦手な食材を抜く、あるいは変更する柔軟性: 可能であれば、お客様のリクエストに応じて、特定の食材を抜いたり、別の食材に変更したりするなどの柔軟な対応を検討します。
- 外国人観光客向けのセットメニュー開発: 日本の定食スタイルは魅力的ですが、苦手なものが含まれていると頼みにくい場合があります。外国人観光客が比較的抵抗なく食べられるものを組み合わせた、お試しセットやおすすめセットを用意するのも良い方法です。
3.日本の食文化を伝えるコミュニケーション
なぜその料理が日本で食べられているのか、どのような歴史や背景があるのかを伝えることで、外国人観光客の理解と興味を深めることができます。
- 食材の旬や産地について説明する: 日本の四季折々の食材や、特定の地域の特産品であることなどを伝えることで、料理への関心が高まります。
- 食べ方を丁寧に説明する: 納豆の混ぜ方や、蕎麦の食べ方など、日本の独特な食べ方を丁寧に伝えることで、戸惑いをなくし、より美味しく味わってもらえます。動画やイラストを使った説明も効果的です。
- 料理にまつわるストーリーを話す: その料理が生まれた背景や、地域との関わりなど、料理にまつわるストーリーを話すことで、単なる食事ではなく、文化体験としての価値を高めることができます。
ある東京の寿司店では、大将が簡単な英語で、その日のネタの説明や、魚が獲れた場所、美味しい食べ方などを客に語りかけます。これにより、外国人観光客は単に寿司を食べるだけでなく、日本の漁業や食文化の一端に触れることができ、深い感動を得ています。
4.体験型コンテンツの提供
食単体だけでなく、食にまつわる体験を提供することも、インバウンド観光客に日本の食文化を理解してもらい、楽しんでもらうための有効な手段です。
- 料理教室: 寿司、うどん、お好み焼きなど、日本の代表的な料理を自分で作る体験は非常に人気があります。自分自身で作ることで、食材への理解や愛着が深まります。
- 市場見学と連携した食事: 地域の市場を見学し、そこで見た新鮮な食材を近くの飲食店で味わう、といった連携企画も魅力的です。
- 日本酒や地ビールとのペアリング体験: 料理と相性の良い日本酒や地ビールを紹介し、試飲体験と組み合わせることで、日本の食の奥深さを体験してもらえます。
特定の地域では、地元の農家と連携し、畑で野菜を収穫し、その場で調理して食べるという体験プログラムを提供しており、これが欧米からの観光客に非常に人気です。食材がどのように作られているのかを知ることで、食への感謝と理解が深まります。
5.ハラール、ヴィーガン、アレルギー対応への真摯な取り組み
多様な食のニーズに対応することは、これからのインバウンド対応において不可欠です。
- 専門知識の習得: ハラール、ヴィーガン、各種アレルギーに関する正しい知識を持つことが重要です。外部の専門家や機関と連携することも有効です。
- 専用調理器具やスペースの検討: ハラール対応やアレルギー対応においては、豚肉やアルコール、アレルゲンとなる食材とのコンタミネーション(混入)を防ぐために、専用の調理器具や調理スペースが必要となる場合があります。できる範囲での対応でも、その努力はお客様に伝わります。
- 信頼できる情報発信: 対応可能なメニューや取り組みについて、ウェブサイトや店頭で明確に情報発信します。お客様からの問い合わせには、誠実に、そして正確に答えるようにします。
ハラール認証を取得している日本のラーメン店や焼肉店は、イスラム圏からの観光客にとって安心して食事ができる場所として知られています。また、ベジタリアン・ヴィーガン対応に特化したカフェやレストランも都市部を中心に増えており、多様な食の選択肢を提供しています。
6.スタッフの教育と多文化理解
最終的に、お客様に心地よく過ごしていただくためには、現場のスタッフの対応が最も重要です。
- 多文化理解の研修: 様々な国や地域の文化、習慣、宗教について学ぶ機会を設けます。食文化の違いについても理解を深めます。
- 基本的な外国語での接客スキル: 主要な観光客の言語(英語、中国語、韓国語など)で、基本的な接客ができるようにトレーニングします。
- お客様への配慮とコミュニケーション: お客様の表情や様子をよく観察し、困っているようであれば積極的に声をかけます。食の好みについて質問したり、おすすめを紹介したりするなど、丁寧なコミュニケーションを心がけます。
- 苦手なものがあった場合の柔軟な対応: もしお客様が苦手な料理に直面した場合でも、非難するのではなく、「もしかしたらお口に合わないかもしれませんね、他に何かお持ちしましょうか?」といった empathetic(共感的な)な言葉遣いで対応します。
ある地方の旅館では、スタッフ全員が地域の食文化や食材について学び、外国人観光客に英語で説明できるように訓練しています。また、お客様の出身国に合わせて、会話のきっかけとなるような話題を準備するなど、パーソナルなおもてなしを心がけており、高い顧客満足度を得ています。
最新トレンド:食の多様化と「体験価値」の追求
インバウンド観光のトレンドは常に変化していますが、近年特に顕著なのは「食の多様化への対応」と「食を通じた体験価値の追求」です。
- 多様な食ニーズへの対応: ハラール、コーシャ、ベジタリアン、ヴィーガン、アレルギー対応だけでなく、グルテンフリー、低アレルゲンなど、個別の健康志向や dietary requirement(食事制限)への対応がますます重要になっています。
- サステナブルな食への関心: 地元の旬の食材を使うこと、食品ロスを減らす努力、環境に配慮した漁業や農業を応援することなど、サステナブルな食への関心が高まっています。料理の背景にあるストーリーとして、これらの取り組みを伝えることも、共感を呼ぶ要素となります。
- 「体験」としての食: 美味しい料理を提供するだけでなく、その料理ができるまでの過程を知る、作る体験をする、食材の産地を訪れるなど、「コト」としての食の体験価値が重視されています。
海外では、食に特化したガイド付きツアーや、有名シェフによる料理教室などが人気を集めています。日本の飲食店も、単に料理を提供する場としてだけでなく、日本の食文化や地域の魅力を伝える「体験の場」として進化していくことが求められています。
貴店のインバウンド対応、次のステップへ
インバウンド観光客が日本の飲食店で「苦手」と感じがちな料理があることは、決してネガティブなことではありません。むしろ、それは貴店がインバウンド対応をさらに深化させ、他店との差別化を図るための大きなチャンスです。
なぜ苦手なのか、その背景にある文化や習慣を理解し、お客様のニーズに寄り添った情報提供やメニューの工夫、そして心温まるおもてなしを提供することで、「苦手」を「新しい発見」に変え、「また日本に来たら、あの店で食事をしたい!」という感動とリピートに繋げることができます。
まずは、この記事でご紹介したポイントの中で、貴店で取り組めることから始めてみませんか? 多言語メニューの見直し、アレルギー情報の整備、あるいはスタッフとの簡単なロールプレイングなど、小さな一歩からでも確実に変化は生まれます。
日本の豊かな食文化を、より多くの外国人観光客に、そして何よりも貴店を訪れたお客様一人ひとりに、心から楽しんでいただくために。
次の記事では、具体的なメニュー改善事例や、外国人観光客の心を掴む「おもてなし英会話」のヒントなど、さらに実践的な内容を深掘りしていく予定です。
貴店のインバウンド対応が、さらなる成功へと繋がることを心より応援しています。