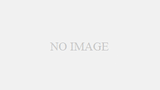前回の記事では、インバウンド観光客の増加がもたらすオーバーツーリズムという状況下で、日本の飲食店が直面する課題と、単に「忙しい」で終わらせないための経営のパラダイムシフトの必要性についてお話ししました。光と影を持つこの状況で、「生き残り」から「選ばれる存在」へと進化するためには、戦略的なアプローチが不可欠であることをご理解いただけたかと存じます。
では、具体的にどのようにすれば、数ある飲食店の中で、観光客にも地元のお客様にも「あのお店に行きたい」「あのお店でなくては」と思ってもらえる、つまり「選ばれる」存在になれるのでしょうか?その鍵を握るのが、「差別化戦略」です。
オーバーツーリズムによって多くの観光客が訪れる場所では、どのお店も賑わっているように見えるかもしれません。しかし、その賑わいが「価格」や「立地」といった表面的な理由によるものだけでは、より安価な店や、より便利な場所にある店に顧客が流れてしまうリスクを常に抱えることになります。このような「埋もれる」リスクを回避し、持続的に顧客を惹きつけるためには、貴社独自の、他の追随を許さない強み、すなわち「突き抜ける」差別化が必要です。
本記事では、この「差別化」をどのように考え、貴社の飲食店(または提携する地域の飲食店)においてどのように実践していくかについて、さらに踏み込んで解説します。単に珍しいメニューを出すといった表面的なことだけでなく、お店のコンセプト、ターゲット顧客、提供する体験全体を通じて、いかに独自の価値を創造するか、具体的なヒントを探っていきましょう。
1. オーバーツーリズム下で「差別化」が生命線となる理由
かつて、日本の地方の飲食店にとって、外国人観光客は「来たら嬉しいボーナス」のような存在だったかもしれません。しかし、今は多くの地域で彼らが主要な顧客層の一部、あるいは大半を占めるようになっています。この変化は大きなチャンスですが、同時に競争環境を激化させています。
オーバーツーリズム下の飲食店は、かつて経験したことのないほど多様なバックグラウンドを持つ顧客と接する機会が増えました。彼らはインターネットやSNSを通じて、事前に膨大な情報を収集しています。価格、料理の種類、立地、評価、写真映え、特別な体験…あらゆる要素を比較検討しています。
このような状況で、他のお店と同じような料理を同じような価格で提供しているだけでは、簡単に「その他大勢」の中に埋もれてしまいます。顧客はより魅力的な選択肢を求めて容易に流出してしまうでしょう。
ここで重要になるのが「差別化」です。差別化とは、単に「他と違うこと」ではなく、「顧客にとって価値のある違い」を創り出すことです。そして、その違いが「なぜ、このお店を選ぶべきなのか?」という問いへの明確な答えとなり、顧客を惹きつけ、繰り返し来店してもらう理由となるのです。
オーバーツーリズムという競争が激しい市場においては、この「選ばれる理由」をいかに明確に打ち出し、顧客に伝えるかが、お店の生き残りを左右すると言っても過言ではありません。それは、単なる「生存」ではなく、「繁栄」への道筋となります。
2. 見つける、磨く、伝える – 貴店だけの「選ばれる理由」(UVP: Unique Value Proposition)
では、貴社の飲食店(または提携先)の「選ばれる理由」、つまりUVP(Unique Value Proposition:独自の価値提案)はどこにあるのでしょうか?これを特定し、磨き上げ、顧客に効果的に伝えるプロセスが差別化戦略の核となります。
UVPを見つけるためには、自店のことを深く掘り下げて考える必要があります。
- お店の「根っこ」は何か?: 創業の想い、店主の料理へのこだわり、長年守り続けてきた伝統、お店の立地する地域の特性など、お店が大切にしている価値観は何でしょうか?
- 誰に、どのような価値を提供したいか?: 理想のお客様はどのような人で、そのお客様がお店に来ることで、どのような良い体験や感情を得られるでしょうか?
- 競合店との違いは何か?: 周囲の飲食店と比べて、料理、サービス、雰囲気、価格帯など、決定的に異なっている点は何でしょうか?それはお客様にとってプラスの違いですか?
- お客様からの声は?: 常連客や、お店を高く評価してくれるお客様は、具体的にどのような点を褒めてくれますか?SNSでの評価や口コミも参考にしましょう。
- 地域の特性との関連は?: そのお店がある地域ならではの魅力と、どのように結びついていますか?地域の歴史、文化、自然、産業など、活用できる要素はありませんか?
これらの問いを通じて見えてきた要素の中から、最も核となる、顧客にとって魅力的で、かつ競合が容易に真似できない部分をUVPとして定義します。
例えば、「新鮮な地元の魚介を使った、漁師町の家庭料理を提供する隠れ家」「築100年の町家で、茶道体験と精進料理が同時に楽しめる静寂の空間」「アニメの聖地巡礼者が集まる、キャラクターをモチーフにしたメニューが豊富なカフェ」など、UVPは多岐にわたります。重要なのは、それが「誰に」対して、どのような「価値」を提供するのかを明確にすることです。
見つけたUVPは、磨き上げて、お店のコンセプト、メニュー、サービス、プロモーション、そしてお店の雰囲気全体に一貫性を持って反映させることが重要です。そして、それをウェブサイト、SNS、メニュー表、店内の掲示物、スタッフの言葉など、あらゆるチャネルを通じて顧客に分かりやすく伝える努力をします。
3. ターゲットを絞る勇気 – 「誰に」愛されるお店になるか
オーバーツーリズム下では、あらゆる観光客を取り込みたいと考えがちです。しかし、「誰にでも好かれよう」とする戦略は、結果として「誰の心にも深く刺さらない」お店になってしまうリスクがあります。むしろ、特定の顧客層に深く愛されるお店になることこそが、差別化に繋がります。
これは、他の顧客層を排除するという意味ではありません。ターゲット顧客を明確にすることで、その層のニーズに最適化されたサービスや体験を提供できるようになり、結果として顧客満足度が高まり、良い口コミが広がりやすくなるのです。
「誰に」愛されるお店になるかを考える際のヒントです。
- 食の嗜好で絞る: 特定の料理ジャンルに特化する(例:ヴィーガン、グルテンフリー、ハラール、特定の郷土料理)、特定の食材にこだわる(例:マグロ専門、ジビエ料理)、特定の調理法を追求する(例:炭火焼き専門、発酵食品中心)など。
- 体験のスタイルで絞る: 静かにゆっくり食事したい層、賑やかな雰囲気で楽しみたい層、料理人と交流したい層、地域の文化に深く触れたい層など、提供したい体験の質やスタイルでターゲットを絞ります。
- 滞在目的で絞る: 観光で訪れた人、ビジネスで訪れた人、特別な記念日で利用したい人など、顧客の来店目的を想定してサービスを最適化します。
- 出身国・文化圏で絞る: 特定の国や地域の文化に合わせたサービスや情報提供を行うことで、その国の観光客にとって「利用しやすい」「安心できる」お店になります。例:中国語対応の強化、特定の祝日に合わせたメニュー提供など。
- 価格帯で絞る: 高価格帯で特別な体験を提供するのか、手頃な価格で日常的な美味しさを提供するのか、明確なポジショニングを行います。
ターゲットを絞ることは、マーケティング資源を効果的に集中させるためにも重要です。例えば、特定の国の観光客をターゲットとするなら、その国で人気のSNSで情報発信したり、その国の旅行会社と連携したりといった施策が考えられます。
ニューヨークのあるレストランは、あえて「地元ブルックリンの人々」を主要なターゲットに据え、彼らの食文化やライフスタイルに合わせたメニュー開発やイベント開催を行うことで、地元からの強い支持を得ています。結果として、その「地元らしさ」が観光客にとって魅力となり、多くの観光客も訪れるようになりました。ターゲットを絞りつつも、他の層も惹きつける好循環を生んでいます。
4. 地域資源を最大限に活かす – ストーリーが価値になる時
日本には、豊かな自然、多様な食材、独自の文化、そして素晴らしい生産者がいます。これらの地域資源を最大限に活用し、そこにストーリーを乗せることは、オーバーツーリズム下で最も強力な差別化の一つとなり得ます。
観光客は、「その地域でしか体験できないこと」「その地域でしか味わえないもの」を求めています。お店の料理やサービスに地域のストーリーが加わることで、単なる「食事」が「文化体験」へと昇華します。
- 地域食材の「顔」を見せる: 誰が、どこで、どのように作っているのか、という情報を提供します。農家さんの写真や、食材が育つ風景を店内に飾る、メニューに生産者名や産地を記載するといった工夫は、料理の信頼性を高め、顧客に安心感と共感を与えます。京都市内の老舗料亭では、使用する京野菜について、どの契約農家から仕入れているかを詳細に説明し、畑の様子を写真で見せることで、食材へのこだわりと地域の豊かさを伝えています。
- 郷土料理や食文化を再解釈・提供する: その地域に古くから伝わる郷土料理や、特別な日に食べられる料理などを、現代風にアレンジしたり、洗練された形で提供したりします。料理の由来や、それが地域の人々の暮らしにどう根ざしているかといったストーリーを添えることで、外国人観光客にとって非常に教育的で魅力的なコンテンツになります。東北地方のある飲食店では、地元の保存食を現代の食卓に合うようにアレンジしたコース料理を提供し、地域の食文化を発信する拠点となっています。
- 地域の職人や伝統産業と連携: 料理に使用する器に地元の陶器を使ったり、店内の装飾に地元の伝統工芸品を取り入れたり、お店のユニフォームに地元の織物を使ったりするなど、地域の他の産業と連携することも、お店の個性となります。それらを販売したり、工房への見学ツアーを企画したりすることで、新たな収益源にもなり得ます。
地域資源の活用は、単に「地産地消」といったスローガンに留まらず、その背後にある人々の営みや文化的な背景を伝えることが重要です。これにより、顧客は「美味しい料理を食べた」だけでなく、「日本の、この地域の文化に触れることができた」という深い満足感を得ることができます。これは、オーバーツーリズムによる画一化への強力なアンチテーゼとなり得ます。
5. 「体験」をデザインする – 食事以外の付加価値
前回の記事でも触れましたが、オーバーツーリズム下では「モノ消費」から「コト消費」、さらには「トキ消費」(その瞬間・空間を体験すること)へのシフトが加速しています。飲食店においても、提供するのは料理だけでなく、「体験」そのものであるという意識が重要です。
体験をデザインするためには、顧客がお店に入ってから出るまでの全てのプロセスを、どのような感情や感覚で過ごしてほしいかを具体的にイメージします。
- 五感に響く空間づくり: 視覚(内装、盛り付け)、聴覚(BGM、店内の音)、嗅覚(料理の香り、店の空気)、触覚(器の手触り、椅子の座り心地)、味覚(料理そのもの)の全てに意識を向けます。それぞれの要素が、お店のコンセプトや提供したい体験と一貫していることが重要です。
- インタラクションの設計: 店員とお客様、お客様同士の間にどのようなコミュニケーションが生まれることを期待するかを設計します。おすすめを尋ねやすい雰囲気、料理について気軽に質問できる関係性、場合によっては店主がカウンター越しに料理の説明をするなど、人との温かい触れ合いは、特に海外からの旅行者にとって日本の良い思い出となります。
- 特別な瞬間の演出: 誕生日や記念日といった特別な機会での利用に対し、サプライズの演出や記念撮影、特別なデザートの提供などを行います。また、初めて来店したお客様に、お店のストーリーを簡単に紹介するといった小さな心遣いも、記憶に残る体験に繋がります。
- 文化的な要素の組み込み: 食事の提供方法に日本の伝統的な作法を取り入れたり、季節ごとの行事や飾りに合わせた演出をしたり、簡単な箸置き作りや折り紙体験をテーブルで提供したりと、食以外の文化的な要素をさりげなく組み込むことも、体験価値を高めます。
イタリアの有名なリストランテでは、単に料理を提供するだけでなく、ソムリエがワインの歴史やブドウ畑の話を語ったり、デザート時にシェフがテーブルを回ってお客様と会話したりするなど、スタッフ全員が「体験の演出家」として機能しています。これにより、顧客は単なる食事以上の、豊かな時間と空間を過ごすことができます。
6. 価格とサービスで多様なニーズに応える
オーバーツーリズム下では、予算や時間、求めるサービスレベルなど、顧客のニーズは多様化します。全ての顧客に画一的なサービスを提供するのではなく、価格やサービス内容に幅を持たせることも、有効な差別化戦略となり得ます。
- 時間帯によるメニューやサービスの変更: 例えば、ランチタイムは手軽に済ませたい観光客やビジネスパーソン向けに効率的なメニューやセルフサービスを取り入れつつ、ディナータイムはゆっくりとコース料理を楽しみたい層向けに、より丁寧なサービスと落ち着いた空間を提供するなど、時間帯によって提供価値を変えます。
- コース料理とアラカルトの提供: 初めて来店する観光客向けに、お店の看板メニューを組み合わせたコース料理を用意し、注文のハードルを下げる一方で、地元の常連客や、特定のものを食べたい顧客向けに豊富なアラカルトメニューを用意するといった戦略です。
- 予約とウォークインのバランス: 事前に計画を立てたい観光客のためにオンライン予約を充実させつつ、フラッと立ち寄りたい地元客や、急に食事場所を探す観光客のために、一定数のウォークイン席を確保するといったバランスも重要です。ただし、過度なウォークイン対応はオペレーションを混乱させる可能性があるため、システムでの管理や入店ルールの明確化が必要です。
- 価格帯の異なる体験を提供する: 同じお店の中で、カウンター席では高級なコース料理と料理人との会話を楽しむ高価格帯の体験を、テーブル席ではより手軽なアラカルトメニューを提供する、といったように、同じ空間でも異なる価格帯とサービスレベルの体験を提供する手法もあります。これにより、幅広い顧客層に対応しつつ、それぞれに最適な価値を提供できます。
シンガポールのある人気ホーカーセンター(屋台街)の有名店は、行列を解消するためにスマートフォンでの事前注文・呼び出しシステムを導入しました。これにより、限られた時間で食事を済ませたいビジネスパーソンや観光客の利便性を高めつつ、効率的なオペレーションを実現しています。これは、価格は手頃でも、サービス提供の方法で差別化を行った例と言えます。
7. デジタルが差別化を加速する
前回の記事でもデジタル化に触れましたが、デジタルツールは単なる効率化ツールではなく、差別化を加速させる強力な武器となります。
- パーソナライズされた情報提供: 予約システムや顧客管理システムを活用し、リピーターの顧客情報(過去の注文履歴、好み、アレルギーなど)を蓄積・分析することで、来店時に合わせたおすすめメニューの提案や、特別なサービスといったパーソナライズされた体験を提供できます。これは、顧客に「大切にされている」と感じてもらう強力な差別化になります。
- オンラインでのブランド体験デザイン: お店のウェブサイトやSNSを単なる情報提供の場としてだけでなく、お店のコンセプトや雰囲気を伝える「デジタルの入り口」としてデザインします。魅力的な写真、動画、お店のストーリーを伝えるコンテンツなどを通じて、来店前から顧客の期待感を高めます。
- 顧客とのインタラクション強化: SNSのコメントやメッセージに丁寧に返信したり、お客様が投稿したお店に関するコンテンツをシェアしたりすることで、顧客とのエンゲージメントを高めます。チャットボットを活用して、簡単な問い合わせに24時間対応することも、利便性向上に繋がります。
- VR/ARを活用した体験プレビュー: 特に高価格帯の体験や、特別な空間を提供するお店では、VR/AR技術を活用して、来店前に店内や料理の雰囲気をバーチャルに体験してもらうことで、期待感を高め、予約へと繋げることができます。
デジタル技術を効果的に活用することは、物理的な店舗空間や対面でのサービスだけでは実現できない、新たな顧客体験やコミュニケーションの可能性を切り拓きます。これにより、オーバーツーリズム下でも顧客一人ひとりとの関係性を深め、強い絆を築くことができます。
8. 差別化の成功事例から学ぶ(示唆に富む例)
具体的な企業名を出して詳細な戦略を解説するには、その戦略がオーバーツーリズムに特化しているか、そしてそれが一般に公開されている情報であるかなど、確認が必要な点が多岐にわたります。ここでは、国内外で見られる、差別化戦略として示唆に富むいくつかの例を、その戦略のタイプに焦点を当ててご紹介します。
- 「地域文化の掘り下げ型」の例: 京都のある老舗の和菓子店では、単に和菓子を販売するだけでなく、季節ごとの行事や、和菓子に込められた日本の自然観・美意識について、多言語で丁寧に解説する体験プログラムを提供しています。これにより、単なる「お土産購入」から、「日本の文化に触れる体験」へと価値を高め、多くの外国人観光客を惹きつけています。これは、地域の伝統文化と食を結びつけた差別化の成功例です。
- 「ニッチ層特化型」の例: 東京都内のあるレストランは、徹底してヴィーガン料理に特化し、世界中のヴィーガン対応を求める旅行者から高い評価を得ています。メニューの豊富さ、料理の質はもちろん、ヴィーガン文化への理解に基づいたサービスを提供することで、特定の層にとって「なくてはならない」存在となっています。オーバーツーリズムで選択肢が増える中でも、明確なターゲットへの特化は強力な差別化となります。
- 「体験デザイン重視型」の例: バルセロナのあるタパスバーでは、単に美味しいタパスを提供するだけでなく、活気のあるオープンキッチン、シェフと客とのインタラクション、そして立ち飲みスタイルで気軽に他の客と交流できる雰囲気全体をデザインしています。料理はもちろんのこと、その場の「賑わい」と「交流」という体験そのものが付加価値となり、多くの観光客や地元客を惹きつけています。
これらの例から学べるのは、差別化は「何を売るか」だけでなく、「誰に、どのように、どのような体験と共に提供するか」という多角的な視点から生まれるということです。貴社の飲食店が持つユニークな要素に光を当て、それをどのように顧客にとっての価値に変えていくか、深く考えることが重要です。
9. 貴社の差別化戦略を考えるための第一歩
今回の記事では、オーバーツーリズム環境下で飲食店が「選ばれる存在」となるための差別化戦略について掘り下げてきました。貴社の飲食店(または提携先)が、この競争の激しい状況を勝ち抜くために、ぜひ以下の問いについてチームで議論してみてください。
- 貴社の飲食店が最も大切にしている「核」(UVP)は何ですか?それは顧客に明確に伝わっていますか?
- どのような顧客層に、最も深く愛されるお店になりたいですか?その顧客層のニーズや価値観を十分に理解していますか?
- 貴社の立地する地域ならではの資源(食材、文化、歴史など)の中で、まだ活用しきれていないものはありませんか?それをどのようにストーリーとして伝えられますか?
- お客様に提供している「体験」について、料理以外の要素(雰囲気、サービス、インタラクションなど)で、さらに磨きをかけられる点はありますか?
- 価格やサービス内容において、多様な顧客ニーズに応えるための柔軟性はありますか?
- デジタルツールを活用して、お客様との関係性を深めたり、お店の個性を伝えたりするために、どのような可能性がありますか?
これらの問いに対する答えを見つけ、具体的な戦略として落とし込んでいくプロセスこそが、オーバーツーリズムを味方につけ、持続的な成長を実現するための鍵となります。
差別化戦略は、一度立てたら終わりではありません。市場の変化、顧客のニーズの変化、競合店の動向などを常に注視し、戦略を柔軟に見直していくことが重要です。
次回の記事では、今回触れた差別化戦略を実行に移す上で不可欠となる、「効率的なオペレーション構築」と「多様な顧客への対応力を高める方法」、そして「地域との連携をさらに深める具体策」といった、より実務的な側面に焦点を当てていく予定です。